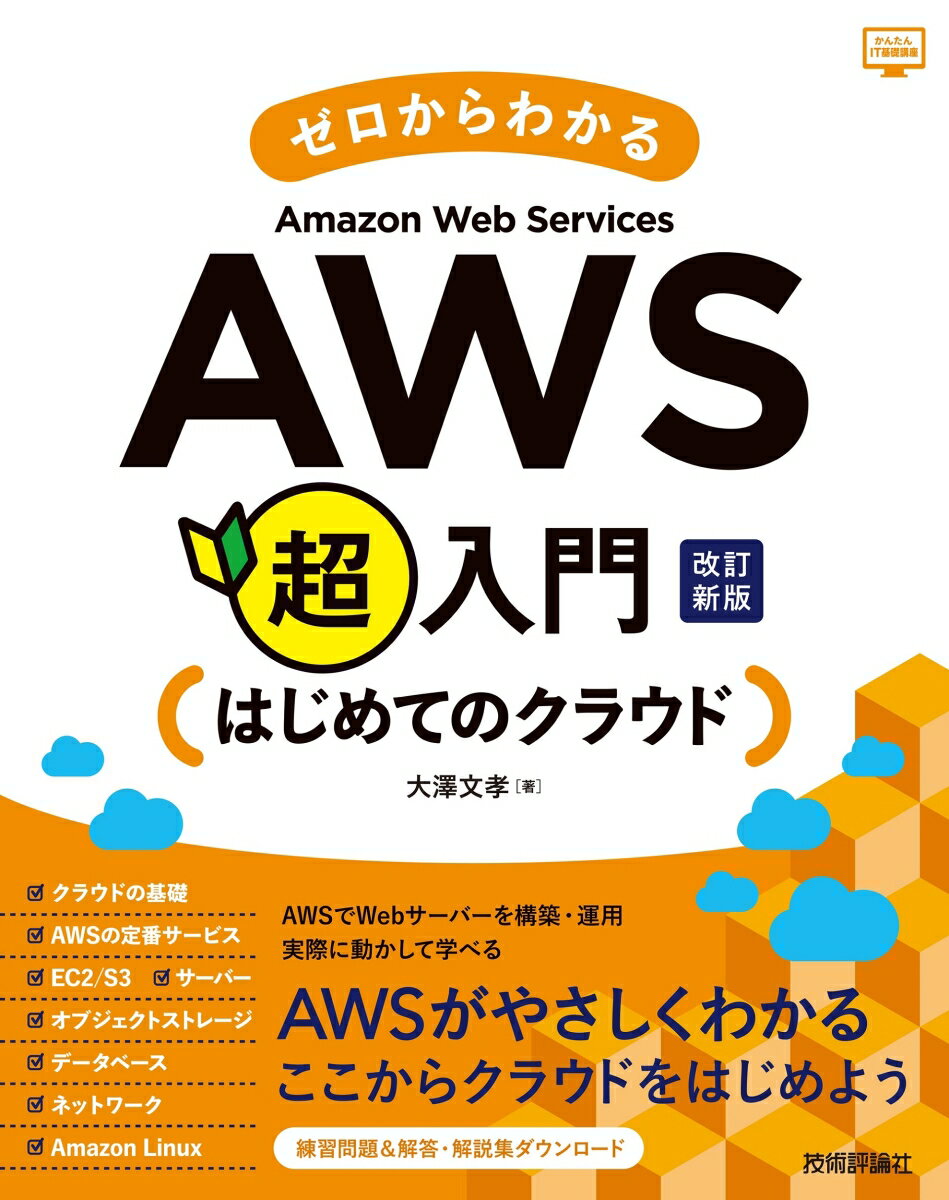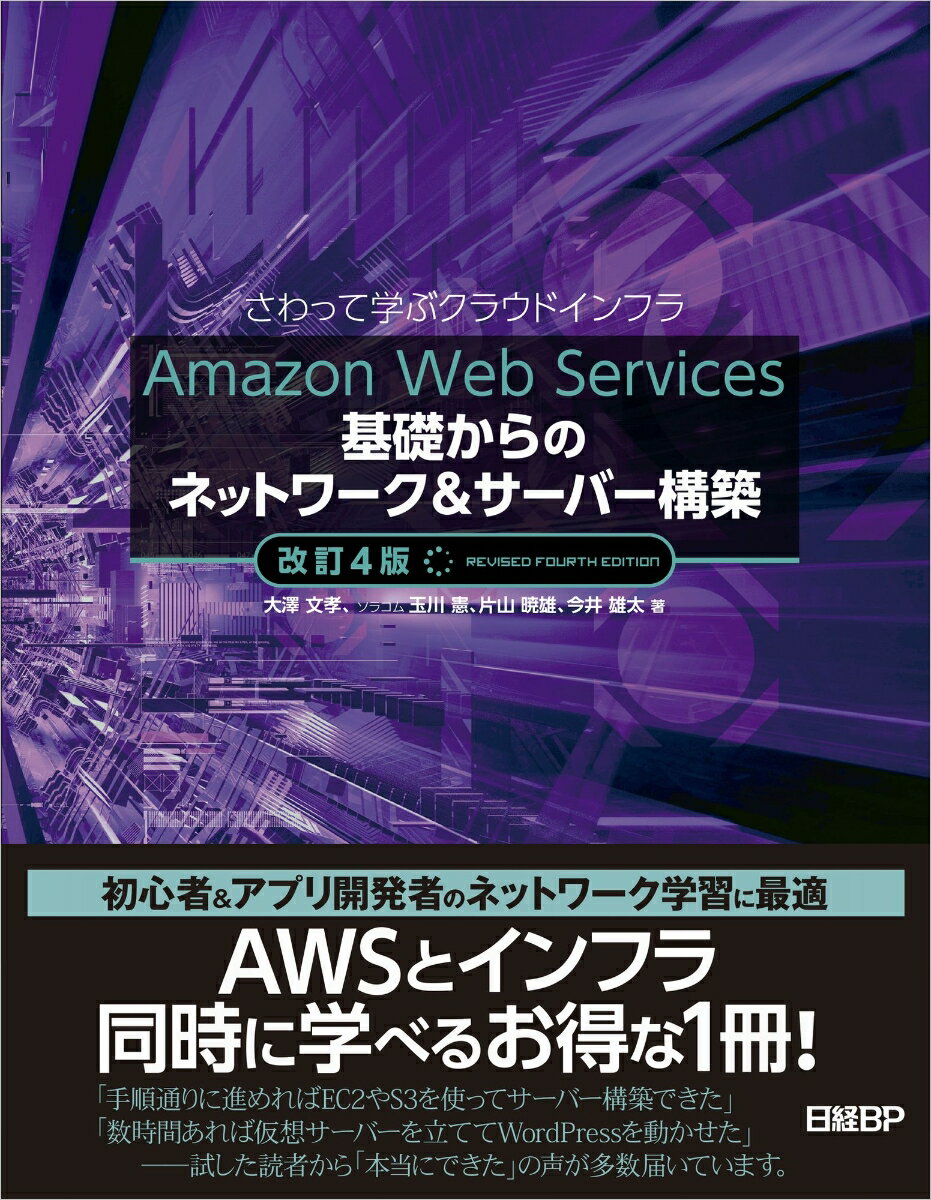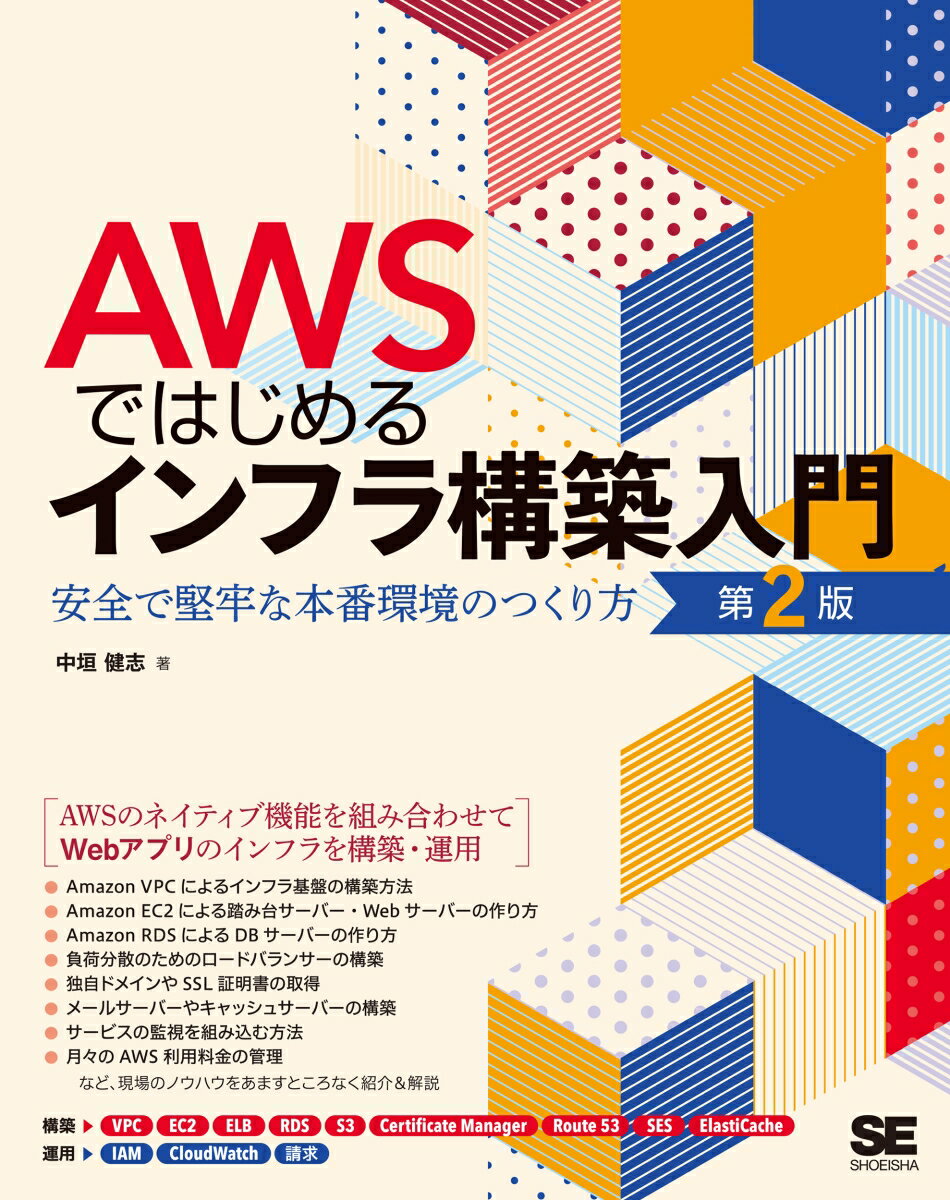※本記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
🐱 < IT知識は調べないとわからないことだらけだよ〜。
「Amazon Web Services(AWS)とは?」
先日AWSで大規模なサーバーダウンが発生しました。多くのウェブサービスやアプリが一時的に使えなくなり、「クラウドってそもそも何?」という疑問を改めて抱いた人も少なくないでしょう。この記事では、AWSの基本を初心者向けに整理しつつ、今回の障害から学べる“クラウドの注意点”も含めて解説します。

ゲームできなくて困ってたぜ。

影響を受けたのが有名どころばかりで仕事にも支障が出そうなレベルね。IT世界の儚さを感じたわ。
クラウドとは何か、そしてAWSの位置づけ
クラウドコンピューティングとは、インターネットを通じてサーバー・ストレージ・ネットワーク・データベースなどのIT資源を“オンデマンド”で利用できる仕組みです。従来、企業が自前でサーバーを用意していた時代から、必要な分だけを借りる形へシフトしており、コスト削減・拡張性(スケーラビリティ)・柔軟性がメリットとされてきました。

その中でも、AWSは世界最大級のクラウドサービスであり、数千・数万という企業・個人がそのインフラを利用してウェブアプリやデータ分析、AI、モバイルバックエンドなどを構築しています。クラウドサービスには Microsoft Azure や Google Cloud などがありますが、AWSはクラウドサービスのなかでも知名度が高く、代表的な存在です。
今回の障害から知る、AWSの“弱点”と注意点
報道によれば、2025年10月20日頃、AWSの米国東部リージョン(us-east-1)でDNS解決やネットワーク系の異常により、一部サービスが利用不能となったとの報告があります。
多数のオンラインサービスが一時利用不能となり、クラウドのインフラ依存の高さが改めて浮き彫りになりました。
この障害から学べる主なポイント:
①リージョン/ゾーン依存のリスク:特定の地域で障害が起きると、そこに集中しているサービスに影響が及びやすい。
②DNS・ネットワーク層の脆弱さ:クラウドでは「見えにくい層」で障害が起きると、影響範囲が極めて広くなる。
③冗長構成とバックアップの重要性:一つのクラウドサービスに全てを任せた構成では、障害時のリスクが大きい。

つまり、ビジネスでAWSのようなクラウドを使うなら、便利さだけじゃなく備え(リージョン分散・障害対策)も重要なのか。
AWSで押さえておきたい初期知識5つ
AWSをこれから学ぶ/使うとき、まず理解しておきたい基本的な構成要素があります。以下に主要な5項目を整理します。
1. リージョンとアベイラビリティゾーン(AZ)
AWSでは世界中に「リージョン」と呼ばれる地理的な区域があり、その中に複数の「アベイラビリティゾーン(AZ)」が存在します。例えばUS-EAST-1は米国東部のリージョン名で、今回の障害で使われていた代表的な場所です。AZやリージョンを分散させることで、ひとつが落ちても他で機能を継続しやすくなります。
2. 主要サービスの役割
- Amazon EC2(仮想サーバー):クラウド上でサーバーを立ち上げてアプリを動かす。
- Amazon S3(オブジェクトストレージ):画像・動画・静的ファイルを格納するサービス。
- Amazon RDS(リレーショナルデータベース):MySQLやPostgreSQLなどをクラウド上でマネージド運用可能。
- AWS Lambda(サーバーレス処理):コードをサーバー管理なしで実行できるサービス。
これらがクラウド環境でシステムを構成する“核”となるサービスです。まずはこれらの機能を押さえると理解が早まります。
3. 費用(コスト)と請求のしくみ
クラウドでは「使った分だけ課金される」従量課金制が一般的です。AWSでも、EC2の稼働時間、データ転送量※、S3の保存容量などがそれぞれ請求対象になります。
障害が起きると稼働停止による機会損失だけでなく、リージョンを跨いだリカバリ構成などでコストが増えることもあります。
※データ転送(特にアウトバウンド)により追加課金されることがある
4. セキュリティと運用の基本
AWSではIAM(Identity and Access Management)という権限管理の仕組みがあり、誰が何をできるかを定義します。また、CloudWatchなどでモニタリングを続けることで“いつ・どこで・どのような異常が起きたか”を把握できます。今回のような障害時には、監視とアラート、災害復旧(DR: Disaster Recovery)構成が鍵となります。
5. 障害時の対応準備
今回の障害のように、クラウドインフラに何らかの障害が発生した場合でも、システム停止を最小限に抑えるための備えがあります。例えば、リージョンの冗長化、マルチクラウド構成、定期的なバックアップ、フェイルオーバーテストなどです。クラウドを使う以上、障害ゼロにはできなくても「ダメージを抑える」設計が必要です。

交通インフラと同じで、トラブル時の復旧まで考慮した設計が必要なのね。
【5選】AWSを学ぶのにおすすめの書籍・教材
AWSは範囲が広く、最初は何から学べばいいか迷いそうです。 ここでは、初心者が体系的に理解を深めるのに役立つ定番書籍・教材を5つご紹介します。
① ゼロからわかる Amazon Web Services超入門 はじめてのクラウド(大澤文孝 著/技術評論社)
クラウドとは何か、AWSの基本的な仕組み、代表的なサービス(EC2・S3など)までをわかりやすく解説した入門書。 初心者でも図解で理解しやすく、AWSを初めて触る人の最初の一冊に最適です。
② AWSの基本・仕組み・重要用語が全部わかる教科書 (見るだけ図解)(川畑光平ほか 著/SBクリエイティブ)
AWSを視覚的に理解できる「見るだけ図解」シリーズ。 EC2やVPCなど、初心者がつまずきやすい概念を豊富なイラストで解説しています。 システム構築をしない人でも“サービスの全体像”をつかむのに最適。
③ 図解即戦力 Amazon Web Servicesのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版](小笠原種高 著)
インフラ構築や設計の現場視点でAWSの全体像を解説する中級者向けの一冊。 「実務でAWSを使うときの考え方」を身につけたい人におすすめです。 図版が多く、技術書が苦手な人にも読みやすい構成。
④ Amazon Web Services基礎からのネットワーク&サーバー構築(改訂4版)
クラウド環境としての Amazon Web Services を “実機代わり” にネットワークとサーバーを構築し学べる入門書です。初心者やインフラをもう一度学び直したいアプリ開発者にも適しており、手を動かしながら理解を深められます。
⑤ AWSではじめるインフラ構築入門 第2版 安全で堅牢な本番環境のつくり方
AWSのネイティブサービス(VPC、EC2、RDS など)を組み合わせて、“安全・堅牢”なクラウドインフラ構築をステップ・バイ・ステップで解説しています。現場で使える構成や運用(監視、コスト管理)までカバーしている一冊。
まとめ:AWSをどう使いこなすか
AWSは非常に強力で、世界中のビジネス・サービスが依存しているクラウドプラットフォームです。しかし今回のような大規模障害が示す通り、“万能”というわけではありません。つまり、クラウドを使う際には「サービスを使える前提」ではなく「使えなくなった時のリスク」を意識すべきです。
初めて触れる方は、まずはリージョン・AZ・EC2・S3・RDSといった基本用語を押さえたうえで、「使いやすさ」だけでなく「運用・監視・コスト・冗長化」という視点も持つと良いでしょう。
どうかこの記事が、あなたのクラウド学習の第一歩として役立てば幸いです。
以上、読んでいただきありがとうございました!